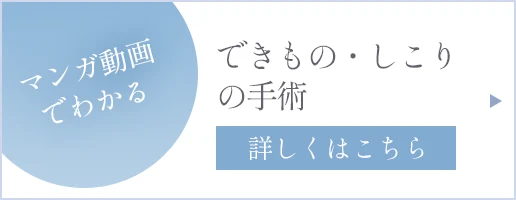粉瘤(アテローム)について
 粉瘤(アテローム)は、皮膚の下にできる良性のできものです。皮脂腺や毛穴が詰まることで形成される袋状の腫れで、中には白色~黄色のどろどろとした内容物(角質や皮脂)が溜まります。
粉瘤(アテローム)は、皮膚の下にできる良性のできものです。皮脂腺や毛穴が詰まることで形成される袋状の腫れで、中には白色~黄色のどろどろとした内容物(角質や皮脂)が溜まります。
放置すると徐々に大きくなることがあり、炎症を起こすと赤く腫れて痛みを伴うことがあります。頭皮、顔、首、背中など皮脂腺の多い部位によくできます。
こんなお悩みはありませんか?
- 皮膚の下に硬いしこりがあり、徐々に大きくなってきている
- しこりを押すと動くが、痛みはほとんどない
- 時々赤く腫れて痛みを感じるようになる
- しこりが破れて白い内容物が出てきたことがある
- 一度治療したが、また同じ場所にできものができた
- できものが目立つ場所にあり、見た目が気になる
など
粉瘤(アテローム)の治療方法
 粉瘤の治療方法は、症状や状態によって異なります。小さく症状がない場合は経過観察をすることもありますが、大きくなったり炎症を起こしたりする場合は治療が必要です。炎症を起こしている粉瘤には、まず抗生物質の内服や外用薬で炎症を抑える治療を行い、その後手術で粉瘤を取り除きます。
粉瘤の治療方法は、症状や状態によって異なります。小さく症状がない場合は経過観察をすることもありますが、大きくなったり炎症を起こしたりする場合は治療が必要です。炎症を起こしている粉瘤には、まず抗生物質の内服や外用薬で炎症を抑える治療を行い、その後手術で粉瘤を取り除きます。
粉瘤を完全に取り除くためには手術が必要で、当院では粉瘤の状態に応じて「くり抜き法」や「切開法」などの適切な手術方法を選択して、日帰りで行っています。
粉瘤(アテローム)の手術
堺市西区の伊谷形成外科・皮フ科クリニックでは、形成外科専門医である院長が粉瘤の状態を詳しく診断して、最適な手術方法を選択します。粉瘤の手術は比較的短時間で行える日帰り手術です。
炎症がない粉瘤に対する「くり抜き法」
炎症がない通常の粉瘤に対しては、通常、「くり抜き法」を行います。粉瘤の中央部または上部に直径2~5mm程度の小さな穴を開けて、専用の器具を使って粉瘤の袋(嚢胞壁)と内容物を一緒に丁寧に取り出します。
傷跡が小さく目立ちにくいため、顔や首など目立つ部位の粉瘤にも適しています。手術時間も短く、多くの場合15分程度で終了します。ただし、大きな粉瘤や複雑な形状の粉瘤では完全摘出が難しいことがあります。
炎症性粉瘤に対する「切開法」
 炎症を起こした粉瘤では、袋が破れて内容物が周囲に漏れ出している場合があります。これを「炎症性粉瘤」と言い、このような場合は「切開法」を選択します。適切な位置に切開を加えて内容物を丁寧に排出して、周囲組織に広がった内容物もしっかり洗浄します。その後、袋(嚢胞壁)を小さくしてから周囲の皮膚とともに切除します。
炎症を起こした粉瘤では、袋が破れて内容物が周囲に漏れ出している場合があります。これを「炎症性粉瘤」と言い、このような場合は「切開法」を選択します。適切な位置に切開を加えて内容物を丁寧に排出して、周囲組織に広がった内容物もしっかり洗浄します。その後、袋(嚢胞壁)を小さくしてから周囲の皮膚とともに切除します。
炎症性粉瘤では「くり抜き法」を行うと再発リスクが高くなるため、通常は「切開法」が適しています。
手術の流れ
1.初診・診察
問診と視診・触診を行い、粉瘤の状態を詳しく評価します。粉瘤の大きさ、位置、炎症の有無、内容物の性状などを確認します。
2.治療方針の決定
診察結果に基づいて、粉瘤の状態に応じた最適な治療方法をご提案します。患者様のご不安やご質問にお答えし、納得していただいたうえで治療計画を立てます。
3.手術当日
お伝えした日時に当院へご来院ください。
4.手術
くり抜き法
- 粉瘤の中央部に小さな穴を開けます
- 専用の器具で嚢胞壁と内容物を丁寧に摘出します
- 出血がないことを確認します
- 必要に応じて縫合を行います
切開法
- 皮膚の皺に沿って切開を加えます
- 内容物を丁寧に排出します
- 嚢胞壁を周囲組織から剥離して完全に摘出します
- 出血点を確認して止血します
- 丁寧に縫合します
術後のケア
 手術後は創部を清潔に保つことが大切です。くり抜き法の場合は傷が小さいため回復も早いですが、切開法の場合は抜糸まで1週間程度かかります。
手術後は創部を清潔に保つことが大切です。くり抜き法の場合は傷が小さいため回復も早いですが、切開法の場合は抜糸まで1週間程度かかります。
術後の経過は定期的な診察で確認し、問題がないか丁寧にフォローします。
術後の注意点
- 当日は激しい運動や入浴を避けてください
- 創部を清潔に保ち、指示された通りに消毒を行ってください
- 痛みがある場合は処方された鎮痛薬を服用してください
- 炎症性粉瘤の場合は、抗生物質の内服を続けることがあります
- 異常な痛み、出血、腫れがある場合はすぐにご連絡ください
など
手術のリスクと合併症
どんな手術にもリスクはつきものです。粉瘤の手術で起こりうる主なリスクと対策についてご説明します。
- 再発:袋が完全に取り除かれていない場合、再発する可能性があります
- 感染:手術後に創部が感染するリスクがあります
- 傷跡:手術による傷跡が残りますが、時間とともに目立たなくなっていきます
- 出血:手術中や術後に出血が生じることがあります
など